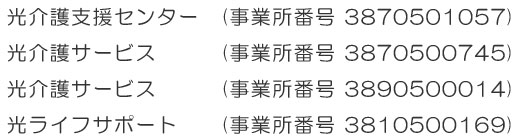(知的障がい者(児)・身体障がい者(児)・精神障がい者)
障害者自立支援法に基づき、障がいのある方が住み慣れた地域で安心した生活ができるようにサポートするサービスです。介護福祉士、ホームヘルパー2級、ガイドヘルパーなどの有資格者がお宅を訪問し生活の支援を致します。
障がい福祉サービスご利用の仕方
1.相談・・・ 市役所または支援事業所へ相談します。
2.申請・・・ 支給の申請を行うと現在の生活や障害の状況についての調査が行われます。
3.審査、判定・・・ 調査の結果を元に市町村で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが 必要な状態か(障害程度区分)が決まります。
4.認定、通知・・・ 障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、決定内容が通知され、受給者証が交付されます。
5.計画相談事業所と契約をします(無料)・・・利用するサービスを決めます。
6.契約・・・ サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
7.サービス利用・・・ サービスの利用を開始します。
訪問介護
身体介護サービス
入浴介護・清拭・洗髪
排泄介護、おむつ交換
食事介護
衣服の着脱の介護
体位変換
通院の介護
家事援助サービス
調理
洗濯
掃除・ごみ出しなど
買い物・薬の受取りなど
その他、関係機関への連絡など必要な家事を行ないます。
介護タクシー
部屋からの移動、タクシー乗降の介護、病院内での移動、受診等の手続きなどのサービスを行います。
行動援護
行動する際に生じうる危険を回避するために必要な介助
外出時における移動の介助
排泄及び食事等の介助
その他外出する際に必要な介助
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等を支援します。
"移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代読、代筆を含む。)を行います。"
排泄、食事等の介助、その他外出する際に必要となる介助を行います。
重度訪問介護
全身障がいがある方など日常生活全般に常時の支援を要する方を対象としたサービスです。
移動支援
屋外での移動が困難な障害者及び障害児について外出の支援を行います。
サービスの時間は午前6時~午後10時までです。
但し、通勤、通学、営業活動等の経済活動等に外出、通年かつ長期にわたる外出には移動支援は利用できません。
その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。
職場環境の改善についてのご紹介
入職促進に向けた取組
共同採用・人事ローテーション・研修制度
- 介護タクシー、自立支援、高齢者介護の3部門が連携し、地域密着型の採用を推進。
- 新人研修や現場同行により、未経験者でも安心して業務に入れるようサポートしています。
幅広い層の人材採用と資格取得支援
- 未経験者・主婦層・中高年も積極採用。年齢や前職を問いません。
- 資格取得に向けて受講費用を補助し、シフト調整で学習時間を確保。
- 有資格者は資格手当で給与面を優遇しています。
資質の向上・キャリアアップ支援
専門研修受講支援
- 介護福祉士・実務者研修・喀痰吸引など、外部研修の参加費用を会社が負担。
- 勤務調整を行い、職員が学びやすい環境を整えています。
研修成果と昇給の連動
- 研修受講 → 人事評価 → 資格手当・昇給に直結する仕組みを構築。
- 学びの成果が正当に評価されることで、継続的なスキルアップを促進します。
両立支援・多様な働き方の推進
短時間正社員・シフト配慮
- 職員の事情や希望に応じて勤務時間・業務内容を柔軟に設定。
- 非正規社員から正社員への登用制度も整備しています。
有給休暇取得促進
- 毎月、有給取得状況をチェックし、取得率の低い職員には上長が声掛け。
- 計画的付与も活用し、休みやすい雰囲気づくりを行っています。
腰痛を含む心身の健康管理
相談窓口の一本化
- ハラスメント・メンタルヘルスの社内相談窓口を一本化し、専任相談員を配置。
- 「困ったときにすぐ相談できる体制」で安心して働ける職場を実現しています。
生産性向上(業務改善・働く環境改善)
事故・トラブル対応マニュアル
- 事故防止マニュアル、苦情対応マニュアルを作成し、誰でも閲覧できるよう設置。
5S活動の徹底
- 整理・整頓・清掃・清潔・躾を定期点検し、「探さない・迷わない」職場を維持。
手順書・書式の改善
- 業務手順書を整備し、記録・報告様式を分かりやすく改訂。
- 利用者情報はノートで共有し、記録用紙を定期的に見直して作業負担を軽減。
やりがい・働きがいの醸成
法人理念の学び直し
- 新人研修だけでなく、年間計画で職場理念・職業倫理・法令遵守を学習。
好事例・謝意の共有
- 毎月のヘルパー会で好事例やご家族の感謝の声を共有し、モチベーション向上。